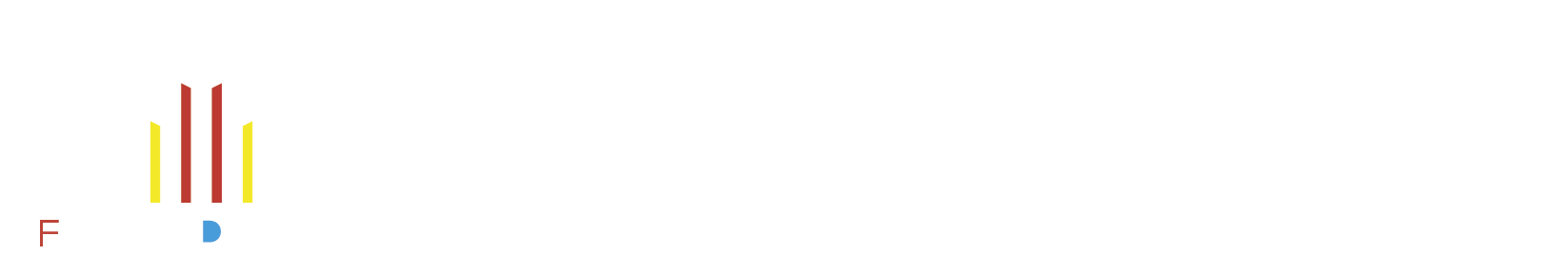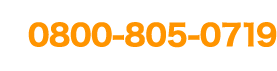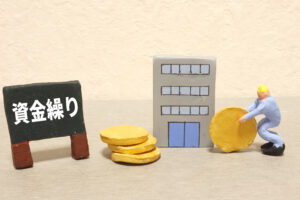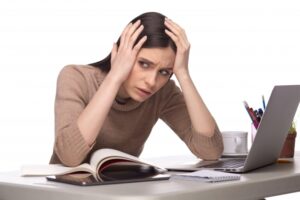決算申告後、北島会計グループでは必ず「決算報告書」というファイルをお渡ししています。これは単なる会計数字の一覧ではなく、会社の1年間の経営活動を数値の形で記録し、未来の経営方針を考えるための重要な資料です。
しかし、多くの中小企業経営者の方々は、決算書や税務申告書を「税務署に提出するもの」と考えがちで、自ら手に取って読み込む機会は少ないのが実情です。
実際には、決算書には経営改善のヒントが数多く隠されており、それらを適切に読み解けば、利益の最大化や資金繰りの改善、事業拡大のための判断材料が得られます。
本稿では、会計と税務の専門家として、経営者が知っておくべき決算書の見方と活用法を、業種別の実例を交えながら解説します。本稿を読むことで、「数字に基づいた意思決定」が実践できる状態を目指していただければと思います。
決算書の基本構造と着目ポイント
決算書は主に貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書の3つで構成され、それぞれ異なる役割を持っています。
貸借対照表は企業の財務状態を切り取った「健康診断書」、損益計算書は一定期間の経営成績を示す「成績表」、キャッシュフロー計算書はお金の流れを可視化する「資金の流れの記録」です。
これらを正しく理解することは、経営判断の出発点となります。
ここでは、貸借対照表と損益計算書について解説します。
貸借対照表(B/S)
貸借対照表は、ある時点における会社の資産、負債、純資産を表します。
たとえば現預金は資金繰りの余裕度を示し、売掛金は今後回収が見込まれる資金を把握する材料となります。
棚卸資産は過剰や不良在庫を抱えていないかを確認するポイントです。
設備投資の状況は有形固定資産に表れ、減価償却の進行具合を知ることができます。
負債の部の買掛金や短期借入金は、今後の支払いで減少する資金を表しています。
利益剰余金は過去からの黒字の積み重ねであり、企業の耐久力を示すバロメーターになります。
<事例>
飲食業を営む株式会社Sは、現預金が月商の0.3か月分しかなく、常に資金ショートのリスクを抱えていました。そこで営業日ごとの売上データを分析し、閑散日はテイクアウト販売に特化。加えて仕入計画を週単位に変更し、冷凍・冷蔵品の回転率を向上させました。
その結果、月商は1.8倍に伸び、現預金は月商の1.5か月分まで増加。廃棄ロスも15%削減され、資金面と利益面の双方で改善が実現しました。
損益計算書(P/L)
損益計算書は、一定期間における売上、費用、利益を明らかにし、会社の収益性や効率性を測る資料です。
売上高は事業規模や成長性を表し、売上原価の水準は原価管理の巧拙を示します。
販売費及び一般管理費では、人件費比率や広告費の効果検証が重要となります。
営業利益は本業からの利益を示すため、ここが赤字であれば早急な対策が必要です。
経常利益は営業外の収益や費用を含めた総合的な利益であり、金融費用の影響が反映されます。
最終的な当期純利益は、税引後に残る利益であり、内部留保の蓄積や将来投資の源となります。
<事例>
IT業の株式会社Cは、営業利益率がわずか3%、人件費率70%という厳しい状況でしたが、自社SaaSを開発し、受託中心からストック型収益構造へ転換。
一人当たり粗利が15%向上し、営業利益率は10%超に改善。利益剰余金も着実に増加しました。
財務指標の見方と業界平均との比較
決算書は単なる数値の羅列ではなく、そこから経営の安全性や収益性を測ることができます。特に財務指標を用いると、会社の現状を客観的に数値化でき、業界の平均値と比較することで、どの部分が強みでどの部分が弱点なのかが見えてきます。
下記に、どの業界でも横断的に有効であり特に中小企業経営者が最初に押さえるべき基本指標を紹介します。
以下の5つの財務指標は、安全性(流動比率・自己資本比率)、収益性(営業利益率・損益分岐点比率)、効率性(総資産回転率)をバランスよく把握できます。
流動比率
1年以内に現金化できる資産と、同じく1年以内に支払う必要のある負債の割合を示すもので、短期的な支払能力を測る指標です。
中小企業では150%以上が望ましいとされ、100%を下回れば資金ショートの危険が高まります。これは、現金や売掛金、棚卸資産といった流動資産と、買掛金や1年以内返済の借入金などの流動負債のバランスで算出されます。
自己資本比率
総資産のうち返済不要な自己資本の割合を示すもので、高いほど財務体質が安定しています。
目安は30%以上ですが、業種によって許容範囲は異なります。たとえば建設業のように手持ち資金が厚い業界では50%近くあることも珍しくありませんが、飲食業のように回転が早く投資負担が軽い業種では20%台でも健全な場合があります。
売上高営業利益率
本業の利益率を示す重要な指標です。この数値が高い企業は、売上を効率的に利益に結びつける仕組みを持っているといえます。
中小企業の目安は5~10%程度ですが、IT業のSaaSモデルなどでは二桁を超えることもあります。
損益分岐点比率
売上高に占める損益分岐点売上高の割合を示す指標です。この比率が低いほど経営の安全性が高いとされます。固定費が高かったり、変動費率が高いと比率は上昇し、利益確保が難しくなります。
※損益分岐点売上高 = 固定費 ÷ { 1 -( 変動費 ÷ 売上高 ) }
総資産回転率
会社が保有する資産をどれだけ効率的に使って売上を上げているかを示します。1.0回転以上であれば、資産を有効に活用できているといえますが、過剰な設備や在庫を抱えている場合はこの数値が下がります。
これらの財務指標はどの業界でも共通して使うことができますが、業界ごとに業態・収益構造が異なりますので、これらの指標の平均値も変わってきます。比較の際は自社と同じ業界の財務指標をご参考ください。
業界ごとの財務指標については、中小企業庁が公表する「中小企業実態基本調査 令和6年確報(令和5年度決算実績)」より調べることができます。
たとえば、飲食業の平均営業利益率は約1.5%、自己資本比率は16%と低水準で、資金繰りの厳しさが数字に表れています。
一方、IT業は営業利益率が約5.9%、自己資本比率は55%超と比較的安定しています。こうした業界平均と自社の数値を比べることで、改善の優先順位を明確にできます。
その他業種別に重要となる指標
業界ごとにビジネスモデルが異なるため、共通指標だけでなく業界特有の視点が重要です。
ここでは飲食業、IT業、内装・土木建築業、アニメ制作業の4つを取り上げています。これは、北島会計グループが多くサポートしている主要顧客層であり、相談ニーズが高い業種だからです。幅広い中小企業の中でも特に課題が顕著で改善余地が大きい分野を選んでいます。
飲食業
飲食業では、原価率・人件費率の管理、客席回転率の向上、そして閑散期対策が重要です。
原価率は30%以内、人件費率は30~35%以内が理想で、これを超えると利益確保が難しくなります。
客席回転率は、1日の総来店客数を席数で割って算出します。これが高ければ限られた席数で効率的に売上を生み出していることになります。
閑散期には、SNS広告を活用してランチやテイクアウトを強化するなどの戦略が有効です。
IT業
IT業では、人件費率の最適化、開発費の資産化、そしてサブスクリプション型ビジネスモデルの構築がカギを握ります。
IT業においては工数管理や一人当たり生産性も重要ですが、「開発費の資産化」を挙げているのは、損益の平準化に直結するからです。多額の開発投資を一括費用計上すると赤字化リスクが高まります。資産計上により費用を複数年に分散させれば、資金繰りや利益指標を安定化でき、金融機関からの信用力も向上します。
また、自社ツールを外販して月額課金モデルを作れば、売上の安定化につながります。
内装業・土木建築業
内装業や土木建築業では、工事原価率の把握、粗利益、未成工事支出金の適正管理 が求められます。元請け依存度が高い場合、工事の時期が偏って資金繰りが乱れることがあります。
また、工事ごとの未成工事支出金の管理が不適切だと、適正な原価管理ができなくなってしまい、場合によっては工事の採算性を正確に把握できず、赤字受注に気づくのが遅れることも考えられます。
アニメ制作業
アニメ制作業では、外注比率の適正化、スタジオ稼働率の向上、著作権収益の確保がポイントです。
工程の一部を内製化して外注依存度を下げる、進行管理を徹底して手戻りを防ぐなど、品質と効率を両立させる仕組みづくりが必要です。
節税と資金繰りの両立
経営指標改善と並び節税は企業経営において重要ですが、資金繰りとはトレードオフの関係になる場合があるため、単年度だけの効果を追い求めると資金繰りに悪影響を及ぼすことがあります。
例えば設備投資で当期の利益を圧縮すれば法人税負担は減りますが、現金支出が先行して発生するため、翌期以降の資金が不足する可能性があります。
また、特別償却や引当金計上などを活用して帳簿上の利益を小さくすると、翌期以降の費用計上の余地が減ってしまいます。
短期的な視点だけでなく、資金繰りの観点からも検討することが重要となります。
どのような節税策が使えるかは会社ごとに異なりますので、気になる方はぜひお問合せください。
おわりに
決算書を 「税務署に出すためのもの」として処理するだけでは、大きな経営改善の機会を失うことになります。これらは経営の羅針盤であり、会社の強みと弱みを示す鏡でもあります。
<事例>
士業向けSaaSを提供する株式会社Bリンクは、部門ごとに利益指標を設定し、行動指標数値と結果に基づいた意思決定を徹底した結果、営業利益率14%、離職率8%、黒字10期連続を達成しました。
一方、アニメ制作下請けの株式会社G制作は、取引単価の交渉に踏み切れず赤字が続き、資金繰りが逼迫しました。最終的には債務超過に陥り、下請け脱却のための戦略も打てないまま事業継続が困難となりました。
上記の事例のように、決算書を正しく活用できるかどうかで企業のその後が大きく変わることもあります。
数字に苦手意識がある経営者の方も、まずは一度、自社の決算書をじっくりと眺め、そこから経営のヒントを探してみてください。会計事務所と共に数字を読み解く習慣を持つことが、安定した成長への第一歩です。
決算書を読み進めるなかで少しでも不安な点があれば、ぜひお気軽にご相談くださいませ。
【会計・税務のお問い合わせ】
お問合せ | 練馬区の税理士 税理士法人北島綜合会計事務所 (tkcnf.com)
【設立のお問い合わせ】
お問合せ | 会社設立サポートセンター練馬 (seturitu-tokyo.com)
【労務のお問い合わせ】
お問合せ|MeiSanbo 練馬区の会計事務所北島管理計算センター